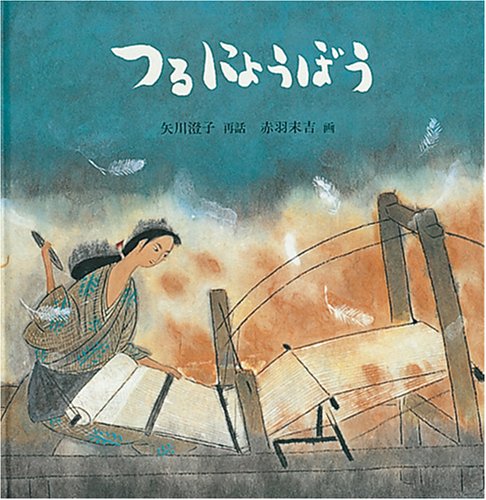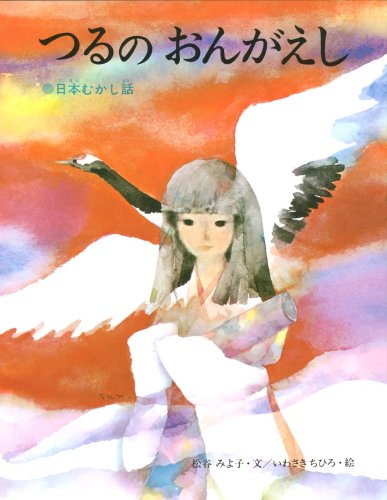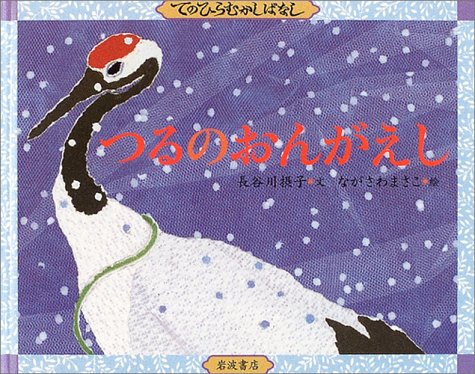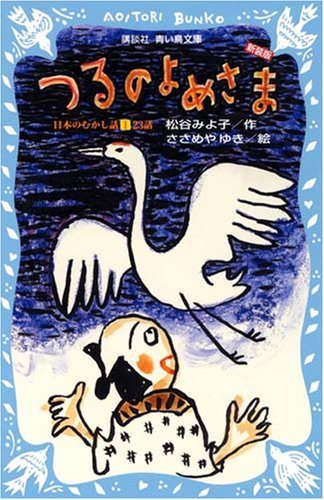『鶴の恩返し』は、「決して覗いてはいけない」という、たった一つの約束さえ守ることのできない人間の愚かさと、日本人が持つ独特の美意識である“はかなさ”を題材にしたお話です。
今回は、『鶴の恩返し』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
 作者不詳である『鶴の恩返し』は、東北地方を中心に伝承されてきた『鶴女房』を基にして作られた民話といわれています。
作者不詳である『鶴の恩返し』は、東北地方を中心に伝承されてきた『鶴女房』を基にして作られた民話といわれています。
昭和24年(1949年)10月に戯曲作家である木下順二の『夕鶴』が初めて公演されて以来、絵本や子ども向け読みもので『鶴の恩返し』として広く知られるようになりました 。
日本の昔話でありながらも、『鶴の恩返し』は海外でも知られています。
イギリス人作家のパトリック・ネスによる小説『The Crane Wife(鶴女房)』と、タイ人作家のポンサコーンによる小説『コン・キモーノー(着物の罠)』は、国境を越え、『鶴の恩返し』の影響を受けた現代小説であるといわれています。
絵本『つるにょうぼう (日本傑作絵本シリーズ)』は、福音館書店から出版されています。人間の心模様の美しさや優しさや悲しさを、矢川澄子さんの文が自然体で表現しています。そして、それを赤羽末吉さんが見事に描いています。情緒あふれる静かで美しい絵本です。 絵本『つるのおんがえし (いわさきちひろの絵本)』は、偕成社から出版されています。広く知られている『鶴の恩返し』とは、少し内容が違います。松谷みよ子さんの文はとても上品で、いわさきちひろさんの描く淡く清楚で苦しみのない絵と重なることで、詩情豊かな絵本という印象です。美しい内容は、日本人の誇りです。 絵本『つるにょうぼう (むかしむかし絵本 7)』は、ポプラ社から出版されています。正体を知られてしまったら、鶴女房は別れなければいけないという、切ない気持ちを、神沢利子さんが、とても美しく言葉で紡いでいます。そして、井口文秀さんの艶やかに描かれた絵によって、お話の物悲しさが増します。巻末には、この絵本を子どもたちに読み聞かせた実践記録が収載されていて、『鶴の恩返し』と『鶴女房』の違いなど、興味深い内容が記されています。 絵本『つるのおんがえし (てのひらむかしばなし)』は、岩波書店から出版されています。手の平サイズなのに、とても読みやすい絵本です。長谷川摂子さんのリズミカルな文と、ながさわまさこさんの味わいあるほのぼのとした“ちぎり絵”の調和が見事な一冊です。 『つるのよめさま ([新装版]日本のむかし話 1)』は、講談社から出版されています。遠い昔に生まれ、長く人々の間で語り継がれてきた昔話には、人間の生きる知恵や生き方の指南が息づいています。松谷みよ子さん・ささめやゆきさんが日本各地で採集し、美しい語り口で再話した「つるのよめさま」をはじめ、「こじきのくれた手ぬぐい」など全23篇が収録された一冊です。 『夕鶴・彦市ばなし』は、偕成社より出版されています。表題の「夕鶴」や「彦市ばなし」の他に「三年寝太郎」や「こぶとり」など、民話から生まれた名作7篇が収録されています。ちなみに、「夕鶴」は劇作家である木下順二の最高傑作と言われています。あらすじ
むかしむかし、あるところに貧しい老夫婦が住んでいました。
ある冬の雪の日、お爺さんが沼の近くで猟師の罠にかかった一羽の鶴を助けました。
するとその夜、旅の途中で道に迷ったので泊めてほしいという美しい娘が老夫婦の家にやってきました。
老夫婦は困っている娘を快く家に入れて、温かいお粥を食べさせてあげました。
娘は、これからどこかへ行く当てがあるわけではないと言うので、老夫婦は娘と一緒に暮らすようになりました。
孝行して老夫婦を助けていた娘が、ある日、
「絶対に中を覗かないでください」
と言って部屋にこもり、機織りを始めました。
そして、三日三晩、不眠不休で、とても美しい布を織り上げました。
お爺さんは、それを売りに街へ行くと、たちまち街で評判となり、高く売れました。
その後も娘は美しい布を次々と織り上げていきました。
そんなある日、娘から機を織る間は覗かないでくれと言われましたが、老夫婦は見事な布を織る娘のことが気になり、機を織っているところを覗いてみると、そこには娘はおらず一羽の鶴がいました。
鶴は自分の体から羽を抜いて布に織り込み、美しい布を作っていたのです。
もう羽毛の大部分が抜かれて、鶴は哀れな姿になっていました。
驚いている老夫婦の前に機織りを終えた娘が、
「私はお爺さんに助けられた鶴です」
と告白し、
「このまま老夫婦の娘でいるつもりでしたが、正体を見られたので、もうお別れのときです」
と言うと、鶴の姿になり、空へと舞い上がっていきました。
解説
古来、日本人は、鶴に馴染んできました。
鶴は、真っ白で、長い脚で立っている姿も、飛翔している姿も、優美にみえる鳥として愛されてきました。
そして、民俗学的にみても、鶴は日本文化において様々な形で表現されています。
民俗学者の柳田国男は、鶴が人間の女に変身して機を織るという着想は、かつて巫女が部屋に籠って供える衣を織っていたことに由来すると指摘しています。
そのため、神聖な機屋を覗き、機を織る姿を見ることは最大の禁忌となり、それは離別につながるそうです。
女性に限らず、人間は秘密を持った生き物です。
どんなに知りたくても、愛する人の過去や秘密を、むやみに暴くようなことをしてはならないと『鶴の恩返し』は伝えようとしているのかもしれません。
感想
一般に『鶴の恩返し』は、「何か良いことをすると必ず別の良いことが自分にかえってくる」という教訓を交えたお話であると考えられがちです。
しかし、実際は、動物を助ける優しさを持ちながらも、「決して覗いてはいけない」というたった一つの約束さえ守れない愚かさを合わせ持った人間の複雑な心理を表しているのではないでしょうか。
つまり、お爺さんに助けられた鶴の報恩より、優しさと愚かさという矛盾する気持ちが同居する人間は、どうしてこんなにも不可思議なのだろうということを、『鶴の恩返し』は切実に説いているのだと思います。
まんが日本昔ばなし
『鶴の恩返し』
放送日: 昭和50年(1975年) 03月04日
放送回: 第0017話(第0009回放送 Aパート)
語り: 市原悦子・(常田富士男)
出典: 表記なし
演出: まるふしろう(藤本四郎)
脚本: 伊東恒久
美術: 内田好之
作画: 上口照人
典型: 動物報恩譚
地域: 中国地方(鳥取県)/東北地方(山形県)/中部地方(新潟県)
最後に
今回は、『鶴の恩返し』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
何かをしているところを「見てはいけない」と禁止が課せられていたにも拘らず、それを破ってしまったために悲劇的な結果が訪れるお話が『鶴の恩返し』です。ぜひ触れてみてください!