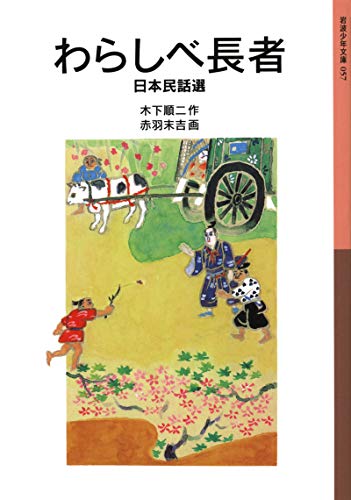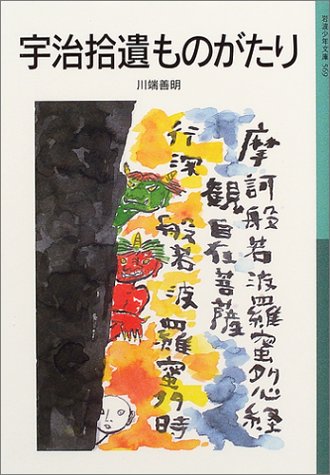『わらしべ長者』は、ある一人の貧乏人が、観音様のお告げを守り、最初に手に入れた“一本の藁(わらしべ)”から物々交換を経ていくにつれて利益を得ていく、不思議でもあり痛快でもある心温まるお話です。
今回は、『わらしべ長者』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
 平安時代末期に成立したとみられる『今昔物語集』および鎌倉時代前期に成立と推定される『宇治拾遺物語』に「わらしべ長者」の原話が記されています。
平安時代末期に成立したとみられる『今昔物語集』および鎌倉時代前期に成立と推定される『宇治拾遺物語』に「わらしべ長者」の原話が記されています。
『わらしべ長者』の舞台は、奈良県桜井市初瀬の長谷寺と伝わります。
鎌倉時代から語り継がれてきた、心温まるサクセスストーリーの『わらしべ長者』は、仏教色の濃い内容のため、おそらく寺僧の説経の素材に用いられたお話ではないかと考えられています。
そして、貧しい男が“一本の藁(わらしべ)”を手に、観音様のお告げを信じて旅に出る姿は、「小さな一歩が大きな未来を切り開く」ことを教えています。
絵本『わらしべちょうじゃ (むかしむかし絵本 17)』は、ポプラ社から出版されています。“一本のわらしべ”から始まり、物々交換によって物が変化していく様を、2ページごとに見て取れるよう工夫がなされています。西郷竹彦さんの文は、短くて分かりやすく、読み聞かせにぴったりのリズム感があり、心に響きます。そして、佐藤忠良さんの鮮やかな色彩と丁寧で細やかな表情が織りなす絵は、子どもたちには夢と知恵を、大人には懐かしさと気づきを与えてくれます。昔話の温かさと現代的な感性が融合しているので、ワクワクしながら物語の世界に引き込まれる素晴らしい一冊です。 絵本『わらしべちょうじゃ (むかしむかし一年生のおはなし 6)』は、ひかりのくにから出版されています。一年生でも理解しやすい言葉遣いで、昔話の奥深さを伝えている松岡節さんのリズミカルで温かみのある文は、読み聞かせに最適です。そして、梶山俊夫さんによる絵は、鮮やかで親しみやすく表情豊かで、特に“一本のわらしべ”から始まる物々交換は、物を交換する際に登場するキャラクターの表情が、ユーモアたっぷりで想像力を刺激し、ページをめくるたびに笑顔になります。単なるサクセスストーリーを描いた絵本ではなく、主人公の純粋さ、機転の利いた行動、そして人との出会いを通じて運が開ける様子は、「誠実さ」や「工夫すること」の大切さを教えています。日本の昔話の魅力を再発見できるよう工夫が満載なので、是非とも手に取ってもらいたい一冊です。 絵本『わらしべちょうじゃ (みんなでよもう!日本の昔話)』は、チャイルド本社から出版されています。日本の児童文学界の巨匠である奈街三郎さんの文は、子どもたちの心に寄り添いながら、主人公の純粋さやユーモラスなやりとりを生き生きと描いているので、想像力が膨らみます。そして、清水耕蔵さんの絵は、表情豊かなキャラクターの明るさや、物々交換の場面をユーモラスに描写しているのに、昔話らしい素朴な雰囲気もあり、物語がさらに楽しくなります。“一本のわらしべ”から始まる大きな冒険は、あなたの心を温かくしてくれる一冊となるでしょう。 絵本『わらしべちょうじゃ (よみきかせ日本昔話)』は、講談社から出版されています。石崎洋司さんの文は、子どもたちが理解しやすい平易な言葉を使い、リズミカルに書かれているので、読み聞かせを通じて語彙力や想像力を育む効果が期待できると共に、考える力を養うきっかけとなることでしょう。そして、ページいっぱいに描かれた西村敏雄さんの絵は、登場人物の表情がとても生き生きと描かれていると共に、夏の日本の風景を鮮やかな色使いで描き出したことで、視覚的な楽しさだけではなく、昔話の世界を現代の子どもたちでも身近に感じることができます。子どもだけでなく、大人も日本の美意識を感じられる一冊です。また、巻末にオマケで『しおふきうす』という昔話が載っています。あらすじ
むかしむかし、あるところに真面目で正直者だけど、何をやっても上手くいかない、運に見放された貧しい男がいました。
そんな貧しい男が、貧乏暮らしを何とかしたいと、観音様にお祈りをしました。
すると観音様が現れ、
「お堂を出たら最初に手にした物を大切にして西へ行きなさい」
と言いました。
男は不思議に思いましたが、お堂を出たとたん転んで一本の藁を手にしました。
それを持って、観音様に言われた通り西へ歩いていくとアブが飛んできたので、男はアブを捕まえると藁の先に縛って歩き続けました。
泣きじゃくる赤ん坊に困った様子のお母さんがいたので、男は手に持っていたアブを縛った藁をあげると赤ん坊は泣き止みました。
すると、お母さんから蜜柑をお礼にもらいました。
蜜柑をもらった男がさらに西へ進んでいくと、木の下に水が欲しくて苦しんでいる娘がいました。
男は持っていた蜜柑を差し出すと、娘の体調は良くなりました。
すると、お礼に上等な絹の布をもらいました。
上機嫌の男はさらに西へ進むと、今度は強引な男に出会いました。
その男は、馬が倒れてしまったために先へ進むことができず困っていました。
そして、上等な絹の布を見ると男は、倒れた馬と上等な絹の布を取り替えて欲しいと言い、上等な絹の布と倒れた馬を無理やり取り替えられてしまいました。
男は懸命に馬を介抱しました。その甲斐あって馬はすっかり元気になりました。
男は馬を連れてまた西へ進むと、大きな屋敷を見つけました。
屋敷の門から、ちょうど出てきた主人が馬を気に入り、馬を千両で譲って欲しいと主人に言われました。
あまりにも多い金額に男は驚いて失神してしまいました。
男を介抱する主人の娘は、なんと以前に蜜柑をあげた娘でした。
主人は、娘を助けた男に対し婿になって欲しいと申し出ました。
観音様のお告げに従い、男は藁一本で長者になりました。
解説
『わらしべ長者』の内容は、広く知られている幸福な結婚を語る「観音祈願型」と、藁三本を千両に変えるという難題を押し付けられる「三年味噌型」と呼ばれる二種類に大別されます。
どちらのお話も大筋はほぼ同じですが、前者は観音様が利益を与える内容であるのに対して、後者はあくまでも富を得るに至るまでのことを主題としています。
『今昔物語集 (角川書店編ビギナーズ・クラシックス)』は、現代語訳と古文の生き生きとしたリズムによって誰もが古典の世界を楽しむことができます。 講談社学術文庫より出版されている『宇治拾遺物語』は、原文と現代語訳、解説が全話収載されています。 『宇治拾遺ものがたり』は、岩波少年文庫から出版されています。昔も今も変わらない人の心のふしぎさを描いた一冊です。現代語訳のみを収載したことで、古文が苦手な人でも物語の展開を知ることができます。感想
「モノの価値は人それぞれ」なので、自分にとって価値がないものであったとしても、他人には大きな価値があるということがあります。
考えは人それぞれです。人には、それぞれ違った好みや個性があるので、一律ではありません。
「十人十色」という言葉がありますが、十人の人に触れると十個の考えに触れることができます。
それは、別のものどうしを別のものだと認識することができるということなので、知識を得ることに繋がります。
たくさんの人に触れ、その考えを思考することで初めて新たに得た知識を自分の中に吸収することができます。
そして、それを吸収したうえで自分がどのように行動するのかということが最も重要なのです。
つまり、このお話は、手に入れたモノをただ持っているだけでは、何も起こらないし何も変わらないということを説いているのではないでしょうか。
吸収した知識を使い、さらに結果まで出すことは簡単なことではありませんが、行動しなければ何もおこりません。とにかく、行動を起こすことが変化を生み出す分岐点なのかもしれません。
まんが日本昔ばなし
『わらしべ長者』
放送日: 昭和50年(1975年) 03月25日
放送回: 第0024話(第0012回放送 Bパート)
語り: 常田富士男・(市原悦子)
出典: 表記なし
演出: まるふしろう
脚本: 小田健也
美術: 内田好之
作画: 上口照人・樋口雅一
典型: 致富譚
地域: 近畿地方(奈良県)
『わらしべ長者』は未DVD化のため「VHS-BOX第1集 第4巻」で観ることができます。
最後に
今回は、『わらしべ長者』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
『わらしべ長者』は、観音様を熱心に信仰すれば、かならず幸せがやってくるという仏教観がよく表れています。まさに「信じる者は救われる」ということを表現したお話です。ぜひ触れてみてください!