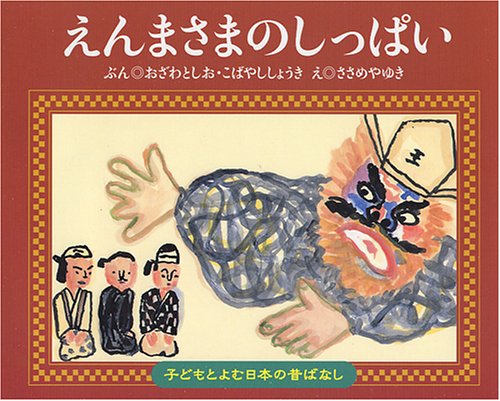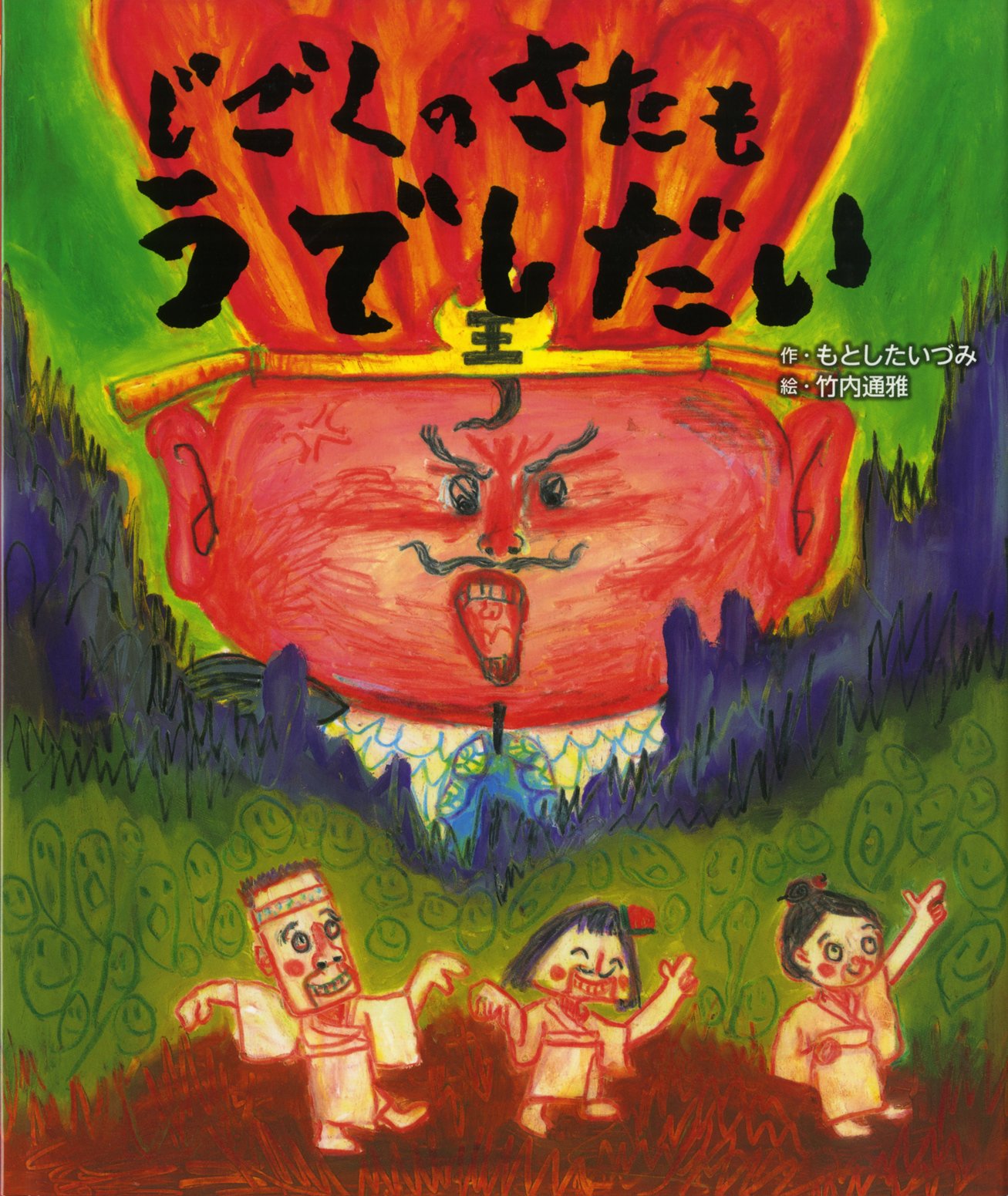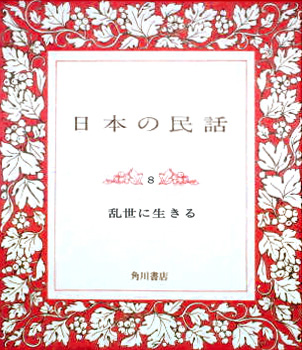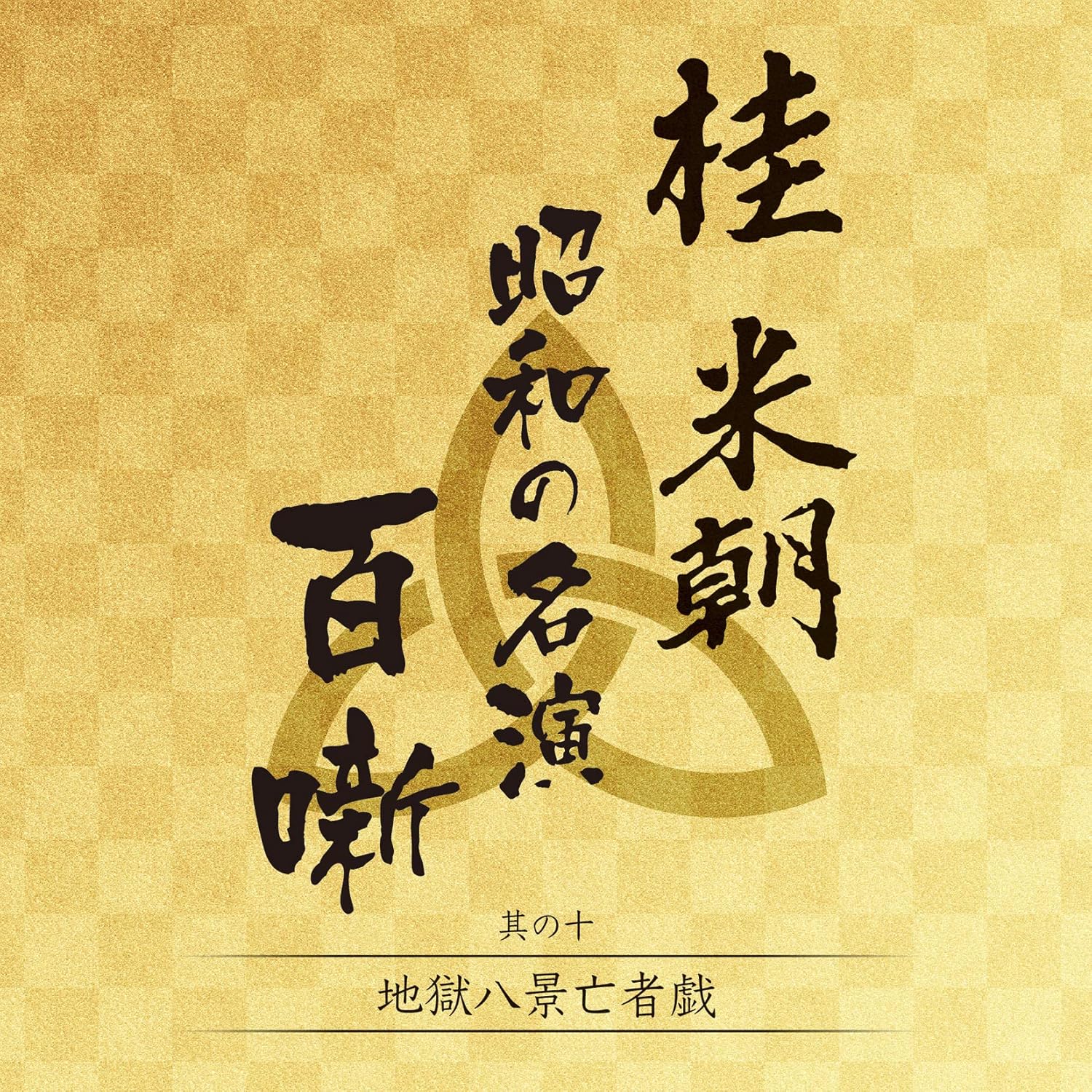運悪く亡くなってしまった医者と山伏と鍛冶屋が、知恵を使って地獄を突き進んでいきます。閻魔大王は、三人をなんとか苦しめようとしますが、あれやこれやと手を使い、三人が閻魔大王と鬼たちを困らせる痛快で爆笑の物語が『地獄のあばれもの』です。
今回は、『地獄のあばれもの』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
『地獄のあばれもの』は、上方では『地獄八景亡者戯』、江戸では『地獄めぐり』という噺として、落語の演目の一つでもある有名なお話です。
『閻魔の失敗』とも呼ばれる『地獄のあばれもの』は、筋立て、結末などに細かな異同はありますが、類話は日本各地に広く伝えられています。
ちなみに、通しで演じると一時間超もある『地獄八景亡者戯』は、上方落語の復興に心血を注ぎ、人間国宝に認定された三代目・桂米朝の十八番の演目としても知られています。
あらすじ
むかしむかし、あるところに一人の医者がおりました。この医者は人の病を治すどころか、自分が病にかかってしまい亡くなってしまいました。
亡くなった人は三途の川を渡り、あの世へ行くのですが、良い行いをしてきた人は極楽へ、悪い行いをしてきた人は地獄へ行くのです。
そして、極楽行きか地獄行きかは、閻魔大王が決めるのでした。
さて、亡くなった医者は、
「閻魔大王様、私は医者でございます。生前は、人々のお役にたつよう精進してまいりました。どうぞ極楽へお願いします」
と閻魔大王に言いました。
閻魔大王は閻魔帳を確認すると、そこには「この医者はヤブ医者だった」と記されていたので、閻魔大王は、
「こら!嘘つきめ!お前はヤブ医者なのに、悪どく儲けておったではないか!お前は地獄行きじゃ!」
と言いました。
医者は鬼につまみ上げられ、ポイッと放り投げられてしまいました。
落ちたところは、地獄へ続く道でした。
「どうせ地獄行きなので、誰か道づれが来るのを待つことにしよう」
と医者は覚悟を決め、かたわらの石に腰をおろしました。
さて、次に閻魔大王のところへ来たのは、山伏でした。
山伏は、
「私は山伏として世の中の災いを取り除いてきました。だから極楽行きでしょう」
と閻魔大王に言いました。
閻魔大王は閻魔帳を確認し、
「こら!嘘つきめ!お前は神仏の祟りといって、多くの人から金を巻き上げていたじゃないか!お前は地獄行きじゃ!」
と山伏に言いました。
山伏も鬼につまみ上げられ、ポイッと放り投げられました。
落ちたところの地獄へ続く道には、医者がおりました。
「二人になったが、もう一人いると心強いな」
と医者が山伏に言うと、
「どうせ地獄行きじゃ。慌てることはない。もう一人来るまで待とう」
と山伏は言い腰をおろしました。
さて、その次に閻魔大王のところへ来たのは、鍛冶屋の親父でした。
「閻魔大王様、私は百姓のために、鎌や鍬など農作業に必要な道具をたくさん作りました。極楽行きでしょう」
と閻魔大王に鍛冶屋は言いました。
閻魔大王は閻魔帳を確認し、
「こら!嘘つきめ!鉄に混ぜ物をして、切れ味が鈍い道具を売っていたじゃないか!お前は地獄行きじゃ!」
と鍛冶屋に言いました。
鍛冶屋も鬼につまみ上げられ、ポイッと放り投げられました。
落ちたところの地獄へ続く道では、医者と山伏がニコニコ顔でお出迎えしました。
「これで三人。では、ぼちぼち参りましょうか」
そんなわけで、三人は連れ立って歩き、地獄の入り口である地獄門へ向かいました。
地獄門では門番である鬼が、
「さっさと入らんか!そして、あの山を登れ!」
と恐ろしい顔で言うので、三人が見ると、なんとそれは鋭い刃物がズラリと並んだ剣の山でした。
「こんな山を登ったら、足が裂けてしまう」
と医者と山伏が怯えていると、
「ここはオラに任しとけ」
と鍛冶屋は言い、剣を一本折って熱で溶かし始めました。
「ほら出来た。鉄の草鞋じゃ。これを履いて歩けば大丈夫」
と鍛冶屋は得意げに言いました。
そして、三人は鉄の草鞋を履いて、剣の山を歩き始めました。
ポキポキと剣がおもしろいように折れるので、三人は後から来る者のために道を作りました。
驚いた鬼たちは、急いで閻魔大王にそのことを伝えました。
「なにぃ!剣の山に道を作っているだと!バカモン!さっさと捕らえて、釜茹でじゃ!」
と閻魔大王は怒りながら言いました。
囚われた三人は、大きな釜の中に放り込まれました。
鬼たちがドンドンと火を焚き、たちまち釜の中はグツグツと煮えたってきました。
医者と鍛冶屋が熱さに耐えていると、
「ここは拙者に任せなさい」
と山伏は言い、何やら呪文を唱え始めました。
「ぬるま湯にな~れ、カァーーーーーッ!」
と山伏が言うと、不思議なことに、お湯はちょうどいい湯加減になりました。
そして、三人はすかっりいい気分となり、釜の中で歌を歌い始めました。
この様子を見て、怒った閻魔大王は、大きな手で三人をひとつかみにすると、三人を一気に飲み込んでしまいました。
三人が落ちたのは、閻魔大王の胃袋の中に落ちました。
「体がとけてきた!」
と山伏と鍛冶屋が怯えていると、医者は落ち着いた様子で、
「心配するな。今、体がとけない薬をつくったで、これを飲みなさい」
と言いました。
その薬を飲むと、たちまち体はシャンとなりました。
そこで、三人は閻魔大王の体の中の探検を始めました。
山伏と鍛冶屋は、上から紐のようなものが幾つもぶら下がっているのを発見しました。
医者がある紐を引っ張ると、閻魔大王は急に笑い出しました。
次に違う紐を引っ張ると、今度は急に閻魔大王は泣き出しました。
わけもなく笑ったり泣いたりする閻魔大王に、鬼たちは気味悪そうに顔を見合わせました。
「こりゃあ、おもしろい」
と体の中の三人は、笑いの紐に、泣きの紐、それから怒りの紐に、くしゃみの紐と、色々な紐を滅茶苦茶に引っ張りました。
「さて、そろそろ下し薬を塗って、外へ出よう」
と医者は、下し薬というものを閻魔大王の体の中に塗りながら言いました。
すると、泣いたり笑ったりしていた閻魔大王は、急に腹をかかえて便所にかけこみました。
そして、閻魔大王のお尻から、医者、山伏、鍛冶屋が、次々と飛び出してきました。
カンカンの閻魔大王は、
「よくもワシに恥をかかせたな!お前たちは、地獄に置いておくわけにはいかない!とっととシャバへ戻れ!」
と言って、三人を地上へ吹き飛ばしてしまいました。
こうして三人は、もう一度この世に舞い戻り、いつまでも仲良く暮らしたそうです。
解説
「三人寄れば文殊の知恵」という格言があります。
これは、凡人であっても、三人で集まって考えれば文殊に劣らないような知恵を出せるという意味になります。
ちなみに、この格言に出てくる文殊とは、文殊菩薩のことで、知恵を司る菩薩とされます。
さて、「三人寄れば文殊の知恵」は、実は学術的には否定されています。
わかりやすい例としては、高度な数学の問題を、凡人が三人集まれば回答できるかというと、それは無理な話です。
現実では、三人のうち、個々で持ち合わせていない知恵が、三人集まることで相互作用が生じるということは、絶対にありえません。
つまり、高度な数学を勉強している一人の専門家に、数学をまったく勉強していない三人が集まったとしても絶対にかなわないということです。
では、「三人寄れば文殊の知恵」の本当の意味はというと、具体的な問題を解決することではなく、誰かと関わることで精神的な安定を得ることができるということではないでしょうか。
不安で胸が張り裂けそうな時は、一人で悩まないで、複数でいることが重要ということです。
感想
人は、必ず死にます。
つまり“必死”ということです。
はかない人生も、必死であるからこそ尊いのです。
お釈迦様の出家の動機は、「死から逃れたい」ということでした。
そして、お釈迦様が出した結論は、「死からは逃れられない」という悟りでした。
では、人は生きているうちに、何をなすべきなのでしょうか。
やはり言えることは、今のこの瞬間をいかに精一杯生きるかに尽きると思います。
それは、全力で生きていること、それ自体が尊いからです。
お釈迦様が「死から逃れたい」ために出家したことから、仏教の根本動機は“死”であるといわれます。
生があれば死があり、生がなければ死もありません。しかし、同時にそれは裏を返せば、死があるから生があり、死がなければ生もないということになります。
この考えを体得し、“必死”であることを心に留めて生きることが、生死を超えていく道であり、豊かな人生のあり方ではないでしょうか。
まんが日本昔ばなし
『地獄のあばれもの』
放送日: 昭和51年(1976年)08月07日
放送回: 第0074話(第0044回放送 Bパート)
語り: 市原悦子・(常田富士男)
出典: 表記なし
演出: 彦根のりお
文芸: 沖島勲
美術: 内田好之(スタジオユニ)
作画: 山崎久
典型: 冒険譚
地域: 関東地方(埼玉県)

Amazonプライム・ビデオで、『まんが日本昔ばなし』へ、ひとっ飛び。
『地獄のあばれもの』は「DVD-BOX第6集 第28巻」で観ることができます。
最後に
今回は、『地獄のあばれもの』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
どんな困難も乗り越えようと、知恵をしぼり力を合わせ、常に前を向くこのと。そして、困難は恐れるものではなく、打ち勝つものであると教えている物語が、『地獄のあばれもの』です。ぜひ触れてみてください!