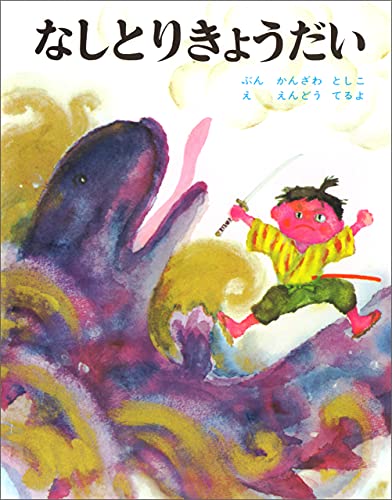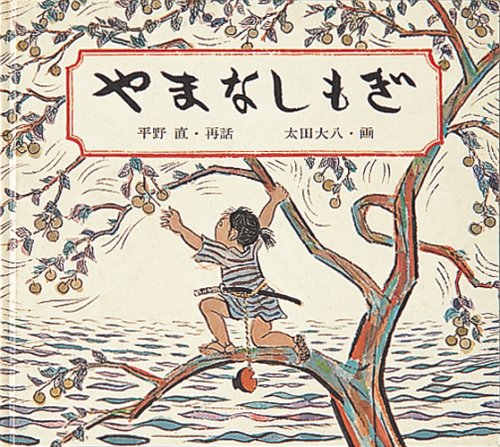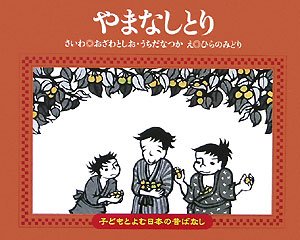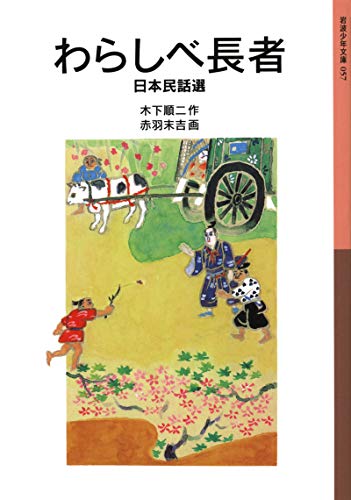「いけっちゃ ガサガサ」
「いくなっちゃ ガサガサ」
『梨とり兄弟』は、三人の兄弟が上から順に病気の母親のために山梨を採るため試練に挑む物語です。冒険の途中、森の中で草木が発する文言とその拍子が、とても楽しく、お話の世界に一気に引き込まれます。
今回は、『梨とり兄弟』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
 『梨とり兄弟』は、江戸時代から語り継がれている民話といわれています。
『梨とり兄弟』は、江戸時代から語り継がれている民話といわれています。
病床に伏せる母のささやかな願いを、兄弟が冒険をして叶える、家族の絆と勇気の物語です。
『梨とり兄弟』は、日本全国に広く分布する民話で、東北地方では『やまなしとり』、近畿地方では『やまなしもぎ』、奈良県近辺では『なら梨採り』と呼ばれ、地域差が面白く、梨の木が身近な土地柄が色濃く反映されていて、まるで日本列島の風土が息づいているようです。
そして、
「行けっちゃ ガサガサ」
「行くなっちゃ ガサガサ」
森の中で草木が発する、この“奇跡の歌”のリズムが、心に楽しく響き、日常の小さな“願い”が、大きな“幸せ”に変わるきっかけになることでしょう。
絵本だけでなく、児童文学なども数多く出版されていますが、特に昭和33年(1958年)に岩波少年文庫より発行された、文: 木下順二・絵: 赤羽末吉の『日本民話選』に収録されている「なら梨とり」は、リズムが良いので、声に出して読むと、心がポカポカ温まると共に、子どもたちの想像を広げてくれます。
絵本『なしとりきょうだい (むかしむかし絵本 4)』は、ポプラ社から出版されています。神沢利子さんによって、とても美しい響きの擬態語や擬音語がたくさん散りばめられています。また、遠藤てるよさんの美しい彩りの絵でお話を描き切っているところも素敵です。何とも言えない、昔話の言葉遣いが面白い絵本です。 絵本『やまなしもぎ (日本傑作絵本シリーズ)』は、福音館書店から出版されています。平野直さんの文は情緒豊かで昔話らしいです。そして、太田大八さんの絵は、不気味さとユーモアが混ざり合っていて、物語の世界にドンドンと引き込まれていきます。何度読んでも飽きない絵本です。 絵本『やまなしとり (子どもとよむ日本の昔ばなし)』は、くもん出版から出版されています。手のひらサイズの絵本です。監修は国際的な昔話の研究家である小澤俊夫さんです。内田夏香さんは、擬態語や擬音語の使い方がとても素晴らしく、それが平野みどりさんの絵とマッチして、とても素敵な絵本となっています。誰もが三男の度胸の良さに胸がすく思いがすることでしょう。あらすじ
むかしむかし、あるところに、お母さんと三人の兄弟が暮らしていました。
ある日、お母さんは重い病にかかってしまいました。
「山梨が食べたい」
とお母さんがつぶやきました。
山梨を食べればお母さんの体が良くなるかも知れない。お母さん想いの兄弟は何とか山梨を食べさせてあげたいと考えました。
一番上の太郎が最初に山梨を採りに山へと向かいました。
太郎がずんずんと山奥へ入っていくと、大きな岩がありました。その岩の上にはお婆さまが座っていました。
お婆さまが、
「この先の三本の枝道になっている所に笹葉が三本生えておる。その笹葉が風に吹かれて、『いけっちゃ ガサガサ』と言う方へ入っていけ」
と教えてくれました。
太郎が山を登っていくと、お婆さまの言う通り三本の枝道がありました。
道の前にはそれぞれ笹葉が生えていて、
左の道の笹葉は
「いけっちゃ ガサガサ」
と葉を揺らしていました。
そして、真ん中と右の笹葉は、
「いくなっちゃ ガサガサ」
と葉を揺らしていました。
しかし、太郎はお婆さまに言われた事を忘れ、真ん中の道を進んでいきました。
そして、沼の主にゲロリと飲み込まれてしまいました。
家ではいくら待っても太郎が帰ってこないので、今度は次郎が山梨を採りに山へと向かいました。
次郎もお婆さまの言う事を聞かず、沼の主にゲロリと飲み込まれてしまいました。
二人の兄はいくら待っても帰ってこないので、三郎も山梨を採りに山へ向かう決心をしました。
三郎は二人の兄とは違い、岩の上にいたお婆さまの話をよく聞きました。
しっかり者の三郎に感心したお婆さまは、一振りの刀を渡しました。三郎はお婆さまに頭を下げると、山へと急ぎました。
しばらく走ると、お婆さまの言う通り三本の枝道がありました。
「いけっちゃ ガサガサ」
「いくなっちゃ ガサガサ」
「いくなっちゃ ガサガサ」
と笹葉が葉を揺らしていました。
三郎は、「いけっちゃ ガサガサ」と笹葉が葉を揺らす左の道を進みました。
三郎がどんどんと進むと沼に着きました。
そこで、どっさり実を付けた山梨の木を見つけました。
「東の側はおっがねぞぉ ザラン」
「西の側はあぶねぇぞぉ ザラン」
「北の側は影がぁうつる ザラン」
「南の側から登らんさい ザラン」
と山梨の実が唄いました。
三郎は山梨の木に南から登り、実をいっぱいもぎ採りました。ところが、あまりに喜んだ三郎は木の反対側から降りてしまいました。そして、沼の水面に三郎が映ってしまいました。
すると、沼の底から沼の主が浮かび上がってきて、三郎をひと飲みにしてしまいました。
ところがどうしたわけか、沼の主はそれから散々苦しんで七転八倒した揚句、完全にのびてしまいました。
それは、三郎がお婆さんに渡された刀で沼の主のお腹を刺したからでした。お腹の中からは三郎と共に太郎と次郎も出てきました。
こうして三郎の大手柄で三人は無事、お母さんの待つ家に帰りました。兄弟が持って帰った山梨を食べると、お母さんの病は治ってしまいました。
そして、お母さんと兄弟三人は、それからもお互いに助け合っていつまでも幸せに暮らしました。
本気で痩せたいなら、ダイエット専門エステ「パーフェクトボディプレミアム」の短期集中プログラムがおすすめ。
パーフェクトボディプレミアムを見る↗︎
解説
古来、森は木の連なりによって出来た空間で、日本人は木を建材や燃料として使用してきました。
しかし、これは森の物理的な側面でしかありません。
もし、日本人が、森に対して単なる物理的な価値しか見いださないのならば、森は不思議な出来事が起こる場所とは考えないはずです。
ところが実際には、人間は思考する生き物なので、日本では、森は聖域とされ、ご神木が存在します。
古来、森は、生命力の強い場所として、日本では言い伝えられてきました。
日本人は、単なる森としての物理的な価値以外の憧れを感じさせるような、精神的な価値を見いだしながら生活してきました。
単なる物質に“神聖”という付加価値を見いだすことは、一見、無駄のように映りますが、実はとても大切な処世術なのです。
それは、辛い時には誰しも心の拠り所を欲するからです。
現実世界を生きていく上で、このような世界観を日本人は常に持ち続けてきたということです。
それから、日本には、古くから自生する野生の梨(ヤマナシ)の存在が、三種確認されています。
主なものは、本州中部地方以南に分布する「ニホンヤマナシ」ですが、東北地方には「イワテヤマナシ(ミチノクナシ)」「アオナシ」が分布し、中部地方には希少な野生種「マメナシ」が分布します。
ニホンヤマナシは、現在、日本で栽培されている多くの梨の原種とされます。
イワテヤマナシ(ミチノクナシ)は、宮沢賢治の童話『やまなし』にも登場し、絶滅危惧種に指定される希少な存在です。
そして、マメナシは、愛知県や三重県などで国の天然記念物に指定され、現在、日本で栽培されている梨の台木として利用されています。
20代・30代の若手に特化!「ツナグバ」は未経験からの転職支援サービスを完全無料で行っております。
ツナグバを見る↗︎
感想
『梨とり兄弟』では、森を登場人物が成長するための経験を積む場所として描かれています。そして、森は「一時的な死と再生の空間」とも描いています。
そう考えると、森を「本来の自分ではなくなる場所」と解釈することができます。
森での修業期間を成長するための試練と考えれば、三兄弟はその時、本来の自分が一時的に死を迎えている状態であり、本来の自分ではない「異なる状態」となります。
つまり「異界にいる状態」といえます。さらに、森は空間的なものだけではなく、時間的なものもあります。「一時的な死の状態」から脱しなければなりません。この森から脱出しなければ「再生」はしないからです。
この様に物語を捉えると、『梨とり兄弟』は日本人が昔から持ち続けてきた多角的視点という感覚を描いた物語だと考えることができます。
多角的視点は、考え方や価値観を豊かにすることができる重要なものです。森のような異界は、私たちが気づかないだけで、実は日常に溢れています。知らない世界観を体験すると視野が広がり、時には新しい発見や嫌いなものを好きになるきっかけを得られることもあります。多角的視点を養える異界を体験して、成長への手掛かりを手に入れましょう。
まんが日本昔ばなし
『梨とり兄弟』
放送日: 昭和51年(1976年)03月13日
放送回: 第0041話(第0023回放送 Aパート)
語り: 常田富士男・(市原悦子)
出典: 表記なし
演出: 高橋良輔
文芸: 沖島勲
美術: 本田幸雄
作画: 竹内大三
典型: 孝行譚・末子成功譚
地域: ある所
『梨とり兄弟』は「DVD-BOX第11集 第53巻」で観ることができます。
最後に
今回は、『梨とり兄弟』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
『梨とり兄弟』は、末っ子が成功を掴み取るという内容で、末子成功譚に分類される昔ばなしです。ぜひ触れてみてください!