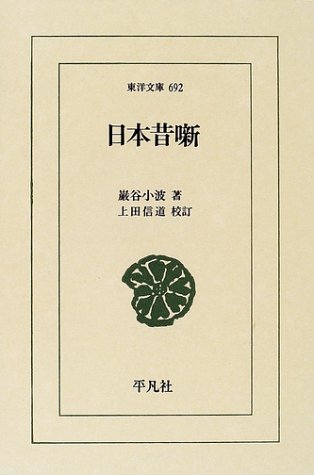助けた亀の報恩によって、『浦島太郎』が海中にある龍宮という異郷を訪れます。龍宮で遊んでいたのは三年の間だったのに、地上の故郷に戻ってくると何百年もの月日が過ぎていたという昔話です。
今回は、『浦島太郎』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
 『浦島太郎』は、奈良時代に成立したとみられる『日本書紀』『丹後国風土記』『万葉集』にとりあげられた同時代の“事件”といわれています。
『浦島太郎』は、奈良時代に成立したとみられる『日本書紀』『丹後国風土記』『万葉集』にとりあげられた同時代の“事件”といわれています。
主人公は丹後国(現在の京都府)の水江浦に住む日下部氏という家の始祖で浦島(のちに浦島太郎)の説話です。
その中でも特に『丹後国風土記』の逸文が、浦島太郎の物語の原型だと考えられています。
近世に入ると子ども向けに脚色され、『浦島太郎』は錦絵などにもなります。
明治時代に入ると幸田露伴、森鴎外、坪内逍遙などの解釈において『浦島太郎』は取り上げられています。
現在、広く知れ渡っている『浦島太郎』は、明治29年(1896年)に児童文学者で俳人の巌谷小波による『日本昔噺』に収録されているお話が広まったものです。
太宰治も昭和20年(1945年)に筑摩書房より発行した『お伽草紙』に「浦島さん」という題で『浦島太郎』を収録しています。
「むかしむかし浦島は~助けた亀に連れられて~」の歌い出しが有名な作詞:乙骨三郎・作曲:三宅延齢の唱歌『浦島太郎』が、明治44年(1911年)の『尋常小学唱歌 第二学年用』に掲載されたことにより昔話と共に唱歌も日本中で広く親しまれています。
絵本『うらしまたろう (日本傑作絵本)』は福音館書店から出版されています。時田史郎さんの文はやわらかくてリズムが良く、秋野不矩さんの絵も美しいです。龍宮へと向かう海の底へ深く潜っていくページでは、本の向きを縦にするなど情景が細かく頭に浮かぶよう工夫されています。 絵本『うらしまたろう (いわさきちひろの絵本)』は偕成社から出版されています。松谷みよ子さんによる独自のアレンジを施したお話といわさきちひろさんの透明感のある絵は、読むと物語の奥の深さを感じることができます。優しくて心が和む絵本です。あらすじ
むかしむかし、あるところに浦島太郎という漁師が年老いた母と二人で暮らしておりました。
ある日、浜辺で子どもたちが一匹の亀をいじめているのを見つけたので、太郎は亀を助けて海へ逃がしてやりました。
すると数日後、亀が現れ、助けてくれたお礼にと亀は太郎を背に乗せて、海の中の龍宮へ連れて行きました。
龍宮では、美しい乙姫様に歓迎され、魚たちの踊りやおいしいご馳走でもてなされ、毎日とても楽しく過ごしました。
しかし三年が経つと、太郎は村に残してきた母のことが気になり、そろそろ村に帰りたいという気持ちになりました。
そのことを乙姫様に伝えると、乙姫様は
「この箱は決して開けてはなりません」
と言って玉手箱を渡し、太郎を送り出しました。
太郎が亀に乗って村に帰ると、自分の家はおろか村の様子がすっかり変わっていて、太郎の知っている人が一人もいなくなっていました。
太郎が龍宮で過ごしているうちに、村は何百年も経っていたのでした。
困った太郎は、約束を破って乙姫様に渡された玉手箱を開けてしまいました。
玉手箱を開けると、中から白い煙がもくもくと出て、たちまち太郎は白い髪を生やしたお爺さんになってしまいました。
解説
平安時代の天長2年(825年)に創祀されたと伝わる京都府与謝郡伊根町本庄浜に鎮座する浦嶋神社は、宇良神社とも呼ばれ、浦島太郎ゆかりの神社とされます。
さて、『浦島太郎』に、初めて「太郎」の名が与えられたのは、鎌倉時代末から江戸時代にかけて成立した『御伽草子』です。
「龍宮」「乙姫」「玉手箱」などの呼称や、浦島が亀を助ける設定は、『御伽草子』に由来するとされます。
ちなみに、『御伽草子』には太郎のその後が描かれています。
それは、太郎が鶴に変化して蓬莱山へと向かい、亀に姿を変えた乙姫が現れ、二人は再会を果たします。
二人は夫婦の明神となり末永く幸せに暮らしたといった内容です。
一説によると、ここから鶴と亀は縁起物であるという風習が広まったといわれています。
感想
現在、広く知れ渡る『浦島太郎』のお話の多くは、「亀を助けた青年が龍宮に招かれ、村に戻った後は老人になる」という内容で描かれています。
この内容だと、「善行は自分に返ってくる」という因果応報の教えを促す道徳的な役割を持ったお話と考えられますが、『御伽草子』で続きを知るとその考えは大きく変わります。
そもそも、広く知れ渡っているお話の内容では、太郎は亀を助けたのに最終的にはお爺さんとなり絶望するという結末であるため、お話が何を伝えたいのかを理解することができません。
しかし、『御伽草子』では、太郎が鶴となり亀に姿を変えた乙姫と結婚して明神となるという恋愛が主筋となるので、多くの部分で辻褄が合うお話となります。
解釈が厄介な玉手箱も人間と動物を繋ぐための大切な道具となります。
つまり、『浦島太郎』は、動物による報恩や因果応報という教訓のお話ではなく、人間と動物が結ばれるお話であり、最後は神になったという起源が語られているということです。
まんが日本昔ばなし
『浦島太郎』
放送日: 昭和50年(1975年) 03月25日
放送回: 第0023話(第0012回放送 Aパート)
語り: 市原悦子・(常田富士男)
出典: 表記なし
演出: 杉井ギサブロー
脚本: 平見修二
美術: 馬郡美保子
作画: 前田庸生
典型: 動物報恩譚・教訓譚(異類婚姻譚・起源譚)
地域: 近畿地方(京都府)
最後に
今回は、『浦島太郎』のあらすじと解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
乙姫は、どうして開けてはいけない玉手箱を太郎に授けたのでしょうか。また、なぜ太郎が龍宮から戻ると何百年もの月日が経っていたのでしょうか。『浦島太郎』を巡る謎には、現代でも多くの推測が飛び交っています。ぜひ触れてみてください!