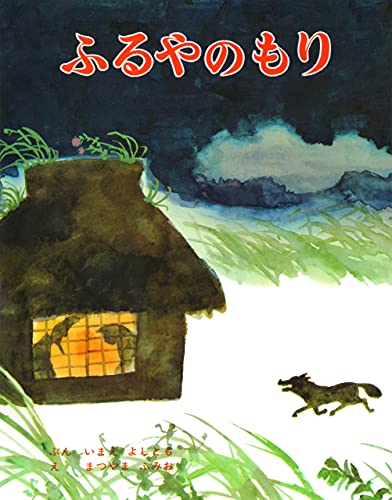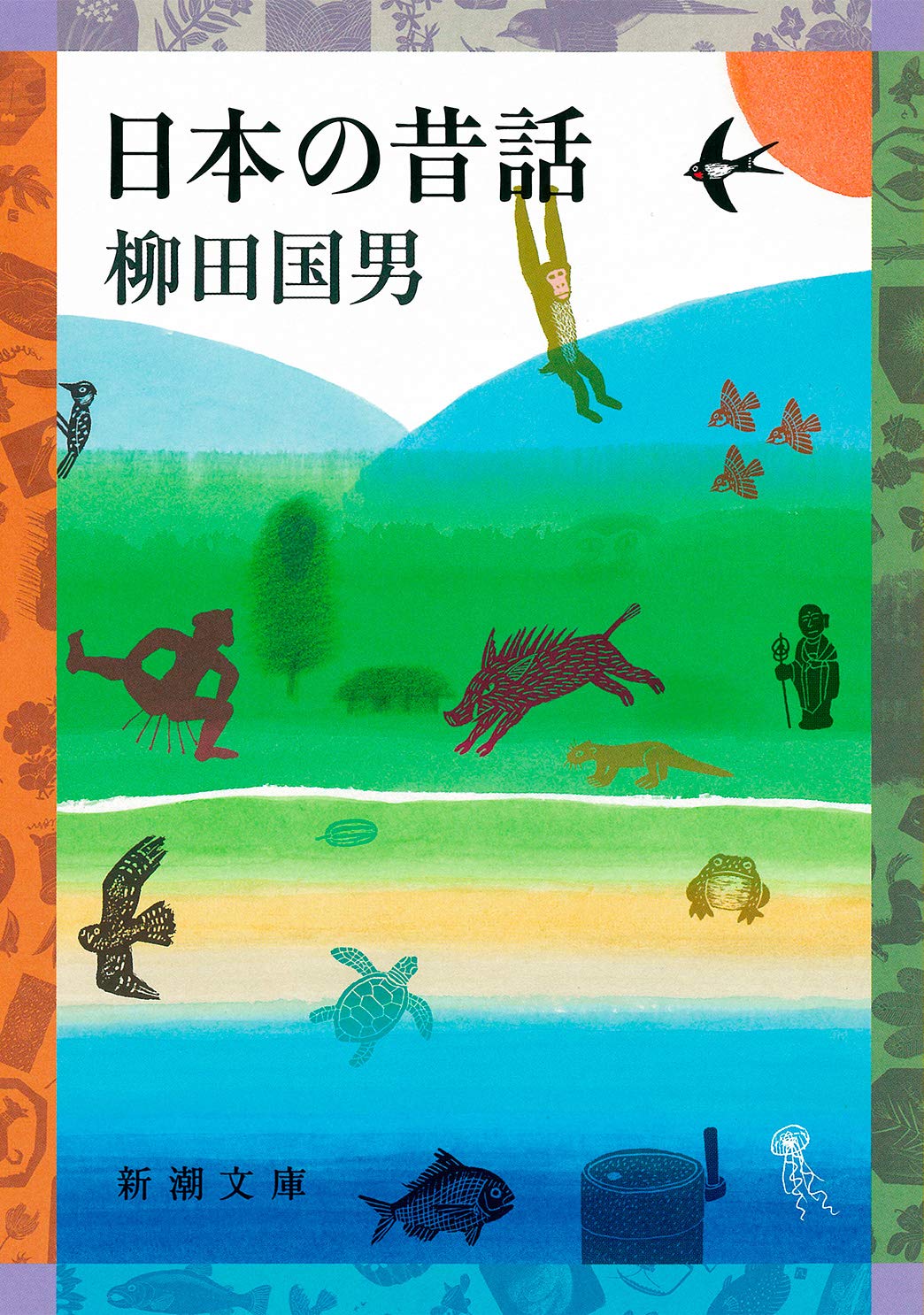言葉の勘違いが引き起こすユーモラスな大騒動!
ふっとした会話を聞いたことで起こる勘違いから、『古屋のもり』の物語は展開します。得体の知れない“ふるやのもり” の恐怖に、慌てふためく泥棒と狼の必死の姿が痛快で、ぐんぐんと内容に引き込まれます。そして、最後は猿の尻尾が短くなった本当の理由に仰天します。
今回は、『古屋のもり』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介します!
概要
 『古屋のもり』は、東北地方に位置する岩手県に伝わる民話です。
『古屋のもり』は、東北地方に位置する岩手県に伝わる民話です。
かなり古い時代から伝承されてきたお話で、中国地方に属する鳥取県や中部地方に属する富山県など、日本各地に同じような内容を持つお話が数多く存在します。
また、中国や東南アジア、インドなどにも同じような内容を持つお話が存在します。
『古屋のもり』の起源は、西暦200年ごろに成立したとされるインドの子ども向け説話集『パンチャタントラ』とされますが、その典拠は不明です。
日本では、江戸時代中期の儒学者である岡白駒が明和5年(1768年)に発行した『奇談一笑』に「屋漏可恐(やもりおそるべし)」という題名で書き残したのが初出と言われています。
昭和16年(1941年)に三国書房より発行された柳田国男の『日本の昔話』に、「猿の尾はなぜ短い」という題名で収録されたことにより『ふるやのもり』は日本中で広く知られるようになりました。
絵本『ふるやのもり(こどものとも傑作集)』は、福音館書店から出版されています。田島征三さんによる暗い色彩で少し怖そうな雰囲気の絵ですが、瀬田貞二さんのスピード感のある面白い文により、いくらでも想像が膨らんで止まりません。子どもたちを惹きつける不思議な魅力がある一冊です。ちなみに、この絵本は、子どもたちの心に残るような強烈な印象の絵本を数々生み出してこられた田島征三さんの絵本デビュー作です。 絵本『ふるやのもり(むかしむかし絵本 10)』は、ポプラ社から出版されています。「ふるやのもり」という魅力的で不思議な響きのある言葉から、鮮やかに話を広げた今江祥智さんの文と、松山文雄さんの繊細にして大胆な絵が重なり合ったことで、読み進めるにつれて物語が一気に加速していく高揚感を覚えます。昔話の面白さがぎっしりと詰まっていて、言葉によって心が踊らされる一冊です。 絵本『ふるやのもり(幼児みんわ絵本 22)』は、ほるぷ出版から出版されています。清水耕蔵さんによる絵が秀悦で迫力満点です。そして、方言を使った今村泰子さんの文は、読み進めるにつれて、難しさよりも“勘違い”による言葉遊びを題材にした物語の独特な雰囲気を壊したくないという気持ちにさせられます。松谷みよ子さんと吉沢和夫さんの監修により、昔話らしい温かみのあって、読んでいて楽しい気持ちになる一冊です。あらすじ
むかしむかし、山奥に古い一軒の家がありました。その家には、お爺さんとお婆さんと、その孫が三人で暮らしていました。生活は貧しく、家の中には何もありませんでした。あるものといえば、馬が一頭いるだけでした。
ある晩、雨が降りそうな暗い夜のことでした。馬を盗もうと、泥棒が家に忍び込み、梁の上に隠れ、家族が寝静まるのを待っていました。
ところが偶然にも、この日は、狼も馬を捕って食おうと家に忍び込み夜が更けるのをじっと待っていました。
お婆さんは孫を寝かしつけようと、いつものようにお話をしていました。
「この世で泥棒より狼より怖いものってなあに」
と孫が尋ねるので、
「それは“ふるやのもり”じゃよ」
「早く寝ないと今夜あたり来るかもしれんのう」
とお婆さんは答えました。
これを聞いていた泥棒と狼は、自分より強い奴がやってくるというので、気が気ではありません。ぶるぶると震えていました。
“ふるやのもり”とは、古い家の雨漏りのことで、お爺さんとお婆さんは雨漏りにとても困っていたのでした。
やがて雨が降ってきて、天井から雨漏りがしてきました。
「“ふるやのもり”が来た」
とお婆さんが叫ぶと、泥棒は驚いて梁から狼の上に落ちてしまいました。
狼は“ふるやのもり”が自分の上に落ちてきたと勘違いし、泥棒を背中に乗せたまま外へ飛び出しました。
泥棒も自分がしがみついているのが“ふるやのもり”だと思い、ふり落とされたら食べられてしまうと必死で狼にしがみつきました。
狼は山中を走り回り、狼の背中にしがみつく泥棒は目に留まった木の枝へ飛び移りました。
狼はそのまま走っていってしまいました。
ほっとした泥棒は、ちょうど木の幹に穴が開いていたので、しばらくそこに隠れることにしました。
ところが、穴が深かったため泥棒は穴の底に落ちてしまいました。
一方、狼は仲間の動物たちに恐ろしい目に遭ったことを話しました。
山一番の知恵者の猿にとっても初めて聞く名前でした。
そこで、狼とともに木の穴に落ちたものが何かを確かめに行くことにしました。
木の幹に開いた穴が怪しいので、猿が長いしっぽを垂らしてみると、穴の中の泥棒は木の蔓だと思い、猿のしっぽにつかまってよじ登り始めました。
驚いた猿は、捕まったら“ふるやのもり”に食べられてしまうと思い、必死に踏ん張りました。
すると、猿のしっぽはぷつんと切れてしまい、その拍子で猿は前につんのめり、顔を擦りむいてしまいました。
それから、猿のしっぽは短くなり、顔が真っ赤になったそうです。
本気で痩せたいなら、ダイエット専門エステ「パーフェクトボディプレミアム」の短期集中プログラムがおすすめ。
パーフェクトボディプレミアムを見る↗︎
解説
『古屋のもり』は、「古い家では雨漏りがする」という、生活に根ざした実感から生まれた民話です。
言葉の勘違いからお話が発展し、最後は猿のしっぽが短くなり顔が赤くなった由来が結末となっています。
雨漏りする茅葺き屋根や藁葺き屋根は、近代化が進み、生活環境が一変した現代の農村地帯では、すっかり姿を消したものばかりです。
そして、現代の子どもたちは、雨漏りと無縁の生活をしています。しかし、雨漏りの鬱陶しさや情景が浮かばない面白さを理解することができないお話でもあります。
また『古屋のもり(古屋の漏り)』は、「秘密のもれることは恐ろしい」という戒めの意味にも用いられます。
20代・30代の若手に特化!「ツナグバ」は未経験からの転職支援サービスを完全無料で行っております。
ツナグバを見る↗︎
感想
『古屋のもり』の面白さは、物語に登場する人物や動物は本当のことを何も知らないのに、物語の読み手や聞き手である私たちはすべてを知っているという仕掛けではないでしょうか。
泥棒も狼もお互いの正体を知りません。
しかし、読者である私たちは、すべてを知っています。
泥棒も狼も“ふるやのもり”が何かを知りませんが、読者である私たちは知っています。
泥棒と猿に関しても同様のことがいえます。
思いがけず、偶然にも誤解や勘違い、信じ込みによって、結び付くはずがないものが結びつくという物語の意外性と、物語に登場する人物や動物と私たち読み手や聞き手との関係が、このお話の可笑しみであり、物語を読み進めることで笑いが生まれるということがいえます。
まんが日本昔ばなし
『古屋のもり』
放送日: 昭和51年(1976年)04月03日
放送回: 第0045話(第0026回放送 Aパート)
語り: 市原悦子・(常田富士男)
出典: 表記なし
演出: 彦根のりお
文芸: 沖島勲
美術: 前島道子
作画: 座間喜代美
典型: 動物昔話・由来譚
地域: 東北地方(岩手県)
『古屋のもり』は「DVD-BOX第9集 第41巻」で観ることができます。
最後に
今回は、『古屋のもり』のあらすじと内容解説、感想、おすすめ絵本などをご紹介しました。
ふっとした会話から始まった勘違いの連続は、滑稽ですが、不思議とちょっと怖くて陰湿な印象を受けません。それは『古屋のもり』が、雨の多い日本らしい「雨漏り」の恐怖がテーマであるのと、「言葉の魔法」が光る物語だからでしょう。ぜひ触れてみてください!